こんにちは!
アンチエイジングアドバイザーのKatsu(@adviserkatsu)です。
今日は、健康を考える上で誰もが一度はぶつかる壁、「栄養バランス」についてお話ししたいと思います。 「体にいい食事をしたいけど、毎日何をどれだけ食べればいいのか、考えるのがもう大変!」 そんな風に感じて、結局いつもと同じような食事になってしまう…なんて経験、ありませんか?
「栄養バランスのよい食事を」という言葉は、とても正しく聞こえる反面、なんだか私たちに「完璧でなければならない」というプレッシャーを与えているような気がします。 栄養素の量を計算して、毎日違う献立を考えて…そんな専門家のようなことを、忙しい私たちが毎日続けるのは、正直なところハードルが高いですよね。
でも、もし栄養バランスを整えるのが、もっと簡単で、もっと楽しい「ゲーム」や「パズル」のようなものだとしたら、どうでしょう? 今回は、難しく考えがちな「栄養バランス」を、誰でも今日から実践できる4つのシンプルな「考え方のツール」としてご紹介します。
あなたの食生活を劇的に変える、4つの「考え方のツール」
栄養バランスを考える方法は、実は一つではありません。 専門家が使うような科学的なデータから、昔ながらの日本の知恵まで、様々なアプローチがあります。 大切なのは、これら全てを完璧にこなすことではありません。 この中から、今のあなたにとって「これならできそう!」と思えるツールを見つけて、試してみることです。
ツール1:食卓をキャンバスに!「彩り」で考える まず最初にご紹介するのは、最も直感的で、ゲームのように楽しめる方法です。 それは、食卓を「キャンバス」に見立てて、できるだけ多くの色で埋めていく、という考え方です。
カラフルな食事は、見た目が華やかで食欲をそそるだけでなく、自然と栄養バランスも整っていく、という素晴らしい特徴があります。 以下の5つの色を意識して、食卓に並べてみましょう。
白:ご飯、パン、うどん、牛乳、ヨーグルト、豆腐、大根など 赤:牛肉、豚肉、ハム、サケ、トマト、にんじん、いちごなど 緑:ほうれん草、ピーマン、ブロッコリー、レタス、キウイフルーツなど 黄:卵、納豆、チーズ、とうもろこし、かぼちゃ、さつまいもなど 黒:わかめ、のり、しいたけなどの海藻やきのこ類、黒ごまなど
どうでしょうか? 「昨日は白と黄色が多かったから、今日は赤と緑を足してみようかな」 そんな風に、パズルを組み立てるように食材を選ぶだけで、自然と様々な食品を摂ることができます。
とはいえ、ただ色を揃えるだけでは、調理法が偏ってしまうこともあります。 例えば、揚げ物が2品、炒め物が2品と重なってしまうと、脂質の摂りすぎが気になりますよね。 「揚げる、炒める、蒸す、ゆでる、生で食べる」など、調理法も様々になるように意識すると、さらに栄養バランスは良くなります。
ツール2:日本の伝統的な知恵!「一汁三菜」で考える 次にご紹介するのは、日本の食文化に古くから根付いている「一汁三菜(いちじゅうさんさい)」という考え方です。 これは、和食の献立の基本となるスタイルで、実は栄養バランスを整えるための、非常に完成されたシステムなんです。
「一汁三菜」の構成は、以下のようになっています。
主食:ご飯やパン、麺類など。主に炭水化物の供給源です。 主菜:メインのおかずです。魚や肉、卵、大豆製品など、主にたんぱく質の供給源となります。 副菜:小さなおかずを2品。野菜やきのこ、海藻などを使ったもので、ビタミンやミネラルを補給します。 汁物:お味噌汁などです。食事全体の水分を補い、主菜や副菜で足りない栄養素を補う役割があります。
この「主食、主菜、副菜、汁物」という型に当てはめて食事を考えるだけで、炭水化物、たんぱく質、ビタミン、ミネラルといった栄養素を、自然とバランスよく摂取することができるのです。
和食がユネスコ無形文化遺産に登録された理由の一つにも、「多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重」や「健康的な食生活を支える栄養バランス」といった点が挙げられています。 旬の食材を使い、だしの旨みを活かして薄味に仕上げる和食のスタイルは、まさに理想的な健康食と言えるかもしれませんね。
ツール3:食品をグループ分け!「三色食品群」で考える もう少しシンプルに、でも論理的に考えたい、という方におすすめなのが、「食品群」で考える方法です。 小学校の栄養教育などでもおなじみの「三色食品群」は、とても分かりやすいツールです。
これは、食品が体の中で果たす主な役割によって、全ての食品を「赤・黄・緑」の3つのグループに分ける考え方です。
赤のグループ:体をつくるもとになる。魚、肉、卵、牛乳、豆類など。 黄のグループ:熱や力になる。ご飯、パン、いも類、砂糖、油脂など。 緑のグループ:体の調子を整える。野菜、果物、海藻、きのこなど。
毎回の食事で、この「赤・黄・緑」の3つのグループがすべて揃っているかチェックするだけ。 これも、とてもシンプルで実践しやすい方法ですよね。
ツール4:専門家の知見!「食事摂取基準」で考える 最後にご紹介するのは、少し専門的なツールです。 厚生労働省が策定している「日本人の食事摂取基準」というものがあります。
これをものすごくざっくりいうと、「健康を維持・増進するために、どの栄養素をどれくらい摂れば良いか」を、科学的なデータに基づいて示した、国の公式ガイドラインです。 年齢や性別ごとに、エネルギーや各栄養素の推奨量や上限量などが細かく定められています。
とはいえ、「毎日この数値をチェックして食事をしましょう!」と言うつもりは全くありません。 これは、どちらかというと栄養士などの専門家が参考にするためのデータです。
ただ、「国が示す、科学的根拠に基づいた基準というものがちゃんと存在するんだな」と知っておくだけでも、巷に溢れる怪しげな健康情報に惑わされにくくなるはずです。 今回ご紹介した「彩り」や「一汁三菜」といったシンプルな方法は、こうした科学的な裏付けの上で成り立っている、と考えていただければと思います。
というわけで
今回は、栄養バランスを考えるための4つのツールをご紹介しました。 いかがでしたでしょうか。「栄養バランス」という言葉が、少し身近に感じられるようになったのではないでしょうか。
大切なのは、これらの方法をすべて完璧に実践することではありません。 「これなら自分にもできそう」「なんだか楽しそう」と思える方法を一つ見つけて、日々の食生活に少しだけ取り入れてみることです。
食卓の彩りを意識するだけでも、一汁三菜の形を真似てみるだけでも、あなたの体は確実に変わっていきます。 難しく考えず、楽しみながら、自分なりの「バランス」を見つけていきましょう。
\ 一人で悩んでいませんか?お気軽にご相談ください! /
アンチエイジングアドバイザー Katsuの無料相談窓口
記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます!
「体に良いとは分かっているけど、続けるのが難しい…」 「情報が多すぎて、何から始めたらいいか分からない」 「私のこの不調、どうしたらいいんだろう?」
もしあなたが今、そんな風に感じているなら、ぜひ一度お話を聞かせてください。 日々の食事や運動のこと、サプリメントの選び方、ちょっとした体の悩みまで、どんな些細なことでも構いません。
あなた専用の「かかりつけアドバイザー」として、親身にサポートさせていただきます。
【ご相談までの流れ】
- 下のボタンから、まずはLINEで「友だち追加」してください。
- 追加後、トーク画面からスタンプを一つでも送っていただけると、こちらからご挨拶のメッセージをお送りします。
- その後、あなたのペースでご相談内容をお聞かせください。
もちろん相談は無料です。安心して、下のボタンをタップしてくださいね。
▼公式LINEでKatsuに無料で相談してみる 無料で相談してみる
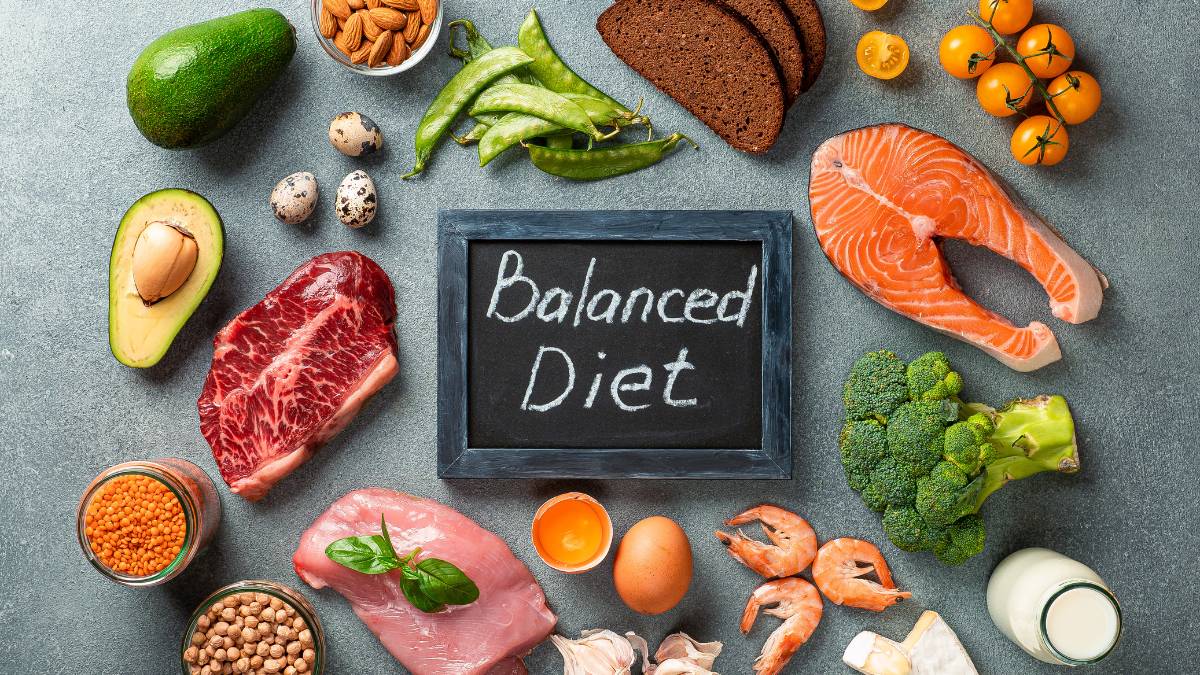
コメント