こんにちは!
アンチエイジングアドバイザーのKatsu(@adviserkatsu)です。
夏の訪れと共に、私たちの心を捉えてやまない、あの香ばしい匂いと、ふっくらとした食感。 日本の食文化の中で、古くから「滋養強壮」「スタミナの源」として、特別な地位を築いてきた食材、ウナギ(鰻)。 特に、夏の土用丑の日には、日本人なら誰もが思い浮かべる、特別なご馳走ですよね。
しかし、その一方で、近年では「高級魚」「絶滅危惧種」といった、少し心配になるような言葉と共に語られることも増えてきました。 私たちにとって、これほど身近でありながら、その生態の多くは、つい最近まで謎に包まれていました。 なぜ、ウナギはこれほどまでに、私たちの心と体を惹きつけるのでしょうか?
今回は、そんなウナギの奥深い世界を、4つのテーマに沿って、その神秘のベールを一枚一枚はがすように、徹底的に掘り下げていきたいと思います。
3000kmを旅する!ウナギの神秘的な生態と、高級魚になった理由
まず、私たちが食べているウナギが、一体どのような魚で、どこからやってくるのか。その驚くべき一生の物語から見ていきましょう。
・ウナギの故郷は、遥か南の海の果て 私たちが日本で主に食べている「ニホンウナギ」は、実は、川や湖で一生を過ごす魚ではありません。 彼らの故郷は、日本から約3000kmも離れた、太平洋のマリアナ海溝の西側にある海山だと、近年の研究でようやく特定されました。 遥か深海で産み落とされた卵から孵化したウナギの赤ちゃんは、「レプトケファルス」と呼ばれる、柳の葉のように透明で、平べったい形をしています。 この姿で、海流に乗って、数ヶ月にも及ぶ、日本への長大な旅を始めるのです。
・「シラスウナギ」への変態と、川での成長 日本の沿岸にたどり着く頃、レプトケファルスは、私たちがニュースなどで目にする、針のように細く透明な「シラスウナギ」へと姿を変えます。 そして、川を遡上し、川や湖といった淡水域で、5年から、長いものでは10年以上もの歳月をかけて、私たちがよく知る、黒いウナギの姿へと成長していくのです。
・再び、故郷の海へ。産卵の旅 そして、十分に成長したウナギは、再び、生まれた故郷の海を目指して、川を下り、3000kmの旅に出ます。 遥かな故郷で、その一生の最後の大仕事である産卵を終え、その命を終えると考えられています。 この、あまりにも壮大で、神秘に満ちたライフサイクルこそが、ウナギという生き物の、最大の魅力の一つなのです。
・なぜ、ウナギは「高級魚」になったのか? かつては、もっと身近な食材であったウナギが、なぜこれほどまでに高騰してしまったのでしょうか。 その最大の原因は、養殖に使うための「シラスウナギ」の漁獲量が、激減してしまったことにあります。 現在、私たちが食べているウナギの99%以上は養殖ものですが、その養殖は、天然のシラスウナギを捕獲し、育てるところからスタートします。 そのシラスウナギが、海洋環境の変化や、河川の堰やダムによる遡上経路の遮断、そして、過剰な漁獲など、様々な要因が複合的に絡み合い、獲れなくなってしまったのです。 ニホンウナギは、現在、IUCN(国際自然保護連合)によって、絶滅危惧種にも指定されています。 私たちが支払う高い価格には、この壮大な生命の物語と、それが今、危機に瀕しているという、重い現実が反映されているのです。
「飲むビタミン剤」!ウナギの驚くべき栄養パワーを解剖する
ウナギが、古くから「滋養強壮」の代名詞とされてきた理由は、その栄養価を詳しく見れば、一目瞭然です。 その身には、まるで「飲むビタミン剤」とでも言うべきほど、多彩で、そして高濃度な栄養素が、ぎっしりと詰まっています。
・ビタミンA:粘膜と免疫の守護神 ウナギの栄養を語る上で、絶対に外せないのが、ビタミンAの圧倒的な含有量です。 ビタミンAは、私たちの体の「バリア機能」を司る、非常に重要なビタミン。 目や鼻、喉、そして胃腸の粘膜を健康に保ち、ウイルスや細菌の侵入を防ぐ、免疫力向上の働きを担います。 夏風邪や、夏場の食欲不振による胃腸の疲れが気になる時に、ウナギが食べられてきたのは、このビタミンAの働きによるところが大きいのです。
・ビタミンB群:エネルギー代謝の最強サポーター ウナギには、エネルギー代謝に不可欠なビタミンB群(B1、B2など)も豊富です。 ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変える際の着火剤。ビタミンB2は、脂質の代謝を助け、皮膚や粘膜の再生を促します。 まさに、夏バテによる疲労回復を、力強くサポートしてくれる栄養素です。
・ビタミンE:若返りのビタミン 強力な抗酸化作用を持ち、体をサビつきから守る、ビタミンEも豊富です。 血行を促進する働きもあり、まさにアンチエイジングには欠かせないビタミンと言えるでしょう。
・EPA・DHA:脳と血管の健康を守る良質な脂質 ウナギの豊かな脂質には、青魚でおなじみの、EPAとDHAも豊富に含まれています。 100gあたりの含有量は、EPAが750mg、DHAが1300mgと、サバやイワシにも引けを取らない、非常に高い数値です。 血液をサラサラにし、血管系の病気を予防するEPAと、脳の機能をサポートするDHA。これらが、40代以降の健康維持に、いかに重要かは、もはや言うまでもありません。
・ムコ多糖類:胃腸を守る「ぬめり」の正体 ウナギの体表の、あの独特の「ぬめり」。その正体は、ムコ多糖類という成分です。 これは、私たちの胃の粘膜にも含まれる成分であり、胃壁を胃酸から守る働きがあります。 ウナギは、脂質が多いにも関わらず、胃にもたれにくい、と言われるのは、このムコ多糖類の働きによるものと考えられています。
その他にも、良質なたんぱく質、骨の健康に欠かせないカルシウムやビタミンDなど、まさに栄養の宝庫。 ウナギが、単なる美味しい魚ではなく、「滋養強壮の食材」として、特別な地位を築いてきた理由が、お分かりいただけるかと思います。
関東風と関西風、あなたはどっち?最高の旬と、究極の食べ方
ウナギの魅力を最大限に引き出す、調理法と、その文化について見ていきましょう。
・ウナギの本当の「旬」とは? 「土用丑の日」の影響で、ウナギの旬は「夏」というイメージが強いですが、実は、天然ウナギが最も美味しくなるのは、秋から冬にかけての時期です。 産卵のために川を下る前の、体に栄養と脂肪をたっぷりと蓄えたこの時期のウナギは、「下りウナギ」とも呼ばれ、まさに絶品です。 夏バテ解消という機能的な側面と、食材としての旬の美味しさには、少しズレがある、というのも面白い点ですね。
・食文化の華「関東風」と「関西風」の違い ウナギの蒲焼の調理法には、関東と関西で、全く異なる文化が発展しました。 ・関東風(江戸前) 武士の文化が根付く関東では、「腹を切る」ことを嫌い、背中から開く「背開き」が基本です。 そして、一度白焼きにした後、「蒸し」の工程が入るのが、最大の特徴。 蒸すことで、余分な脂が落ち、身が驚くほど、ふっくらと柔らかくなります。その後、タレをつけて、優しく焼き上げます。とろけるような食感が魅力です。
・関西風 商人の文化である関西では、「腹を割って話す」ことに通じる「腹開き」が主流です。 そして、蒸しの工程はなく、生のまま串を打ち、炭火で「地焼き」します。 皮はパリッと香ばしく、身は歯ごたえがあり、脂の旨味をダイレクトに味わうことができます。力強い味わいが魅力です。 どちらが良い、悪いではなく、それぞれが、その土地の文化と人々の好みを反映した、素晴らしい調理法なのです。
・蒲焼と白焼き 甘辛いタレをつけて焼く「蒲焼」が一般的ですが、タレをつけずに、塩だけで焼き上げる「白焼き」も、通好みの食べ方です。 ウナギ本来の味を、ワサビ醤油などでシンプルに味わうことができます。 また、タレの糖分やカロリーが気になる方にとっては、カロリーを抑えられる、ヘルシーな選択肢とも言えるでしょう。
平賀源内の発明?「土用丑の日」と、ウナギ養殖の秘密
最後に、ウナギにまつわる、興味深い豆知識をいくつかご紹介します。
・「土用丑の日」は、天才コピーライターの発明だった? 夏の土用丑の日にウナギを食べる、という、今や国民的行事となったこの習慣。 その発端は、江戸時代の天才発明家、平賀源内にある、という説が、あまりにも有名です。 夏場、売り上げが落ちて困っていたウナギ屋に相談された源内が、「本日、土用丑の日」という張り紙を出すことを提案した、というのです。 「丑(うし)の日」に、「う」のつくものを食べると、夏負けしない、という、当時からあった民間伝承に便乗した、この画期的なPR戦略が、見事に大ヒット。 それが、現代にまで続く、一大食文化となった、と言われています。
・なぜ、ウナギの「完全養殖」は難しいのか? ウナギの価格が高騰している最大の理由は、養殖の元となるシラスウナギが、天然資源に依存しているからです。 では、なぜ、マグロのように、卵から育てる「完全養殖」が、商業化できないのでしょうか。 その最大の難関が、ウナギの赤ちゃん「レプトケファルス」の、エサの解明と、長期にわたる飼育の難しさにありました。 何を食べて、どのように成長するのか、その生態は、長年、謎に包まれていました。
・ついに成功!しかし、道はまだ遠い しかし、日本の研究者たちの、長年にわたる、血のにじむような努力の末、2010年、ついに、実験室レベルでの「完全養殖」に、世界で初めて成功しました。 これは、水産研究史における、金字塔とも言える、偉大な成果です。 現在も、より効率的で、低コストな商業化を目指して、研究が続けられています。 近い将来、私たちが、安定した価格で、安心してウナギを食べられる日が来るかもしれません。
ウナギの完全養殖へ大きな一歩。コストが20分の1となる水槽の秘密
・蒲焼と山椒の、切っても切れない関係 蒲焼に、ピリリと刺激的な山椒を振りかける。これもまた、日本の美しい食文化の一つです。 この習慣には、ウナギの生ぐささを消すための薬味としての役割や、山椒が胃腸の働きをよくするため、といった説がありますが、はっきりとした理由は、実は分かっていません。
というわけで
今回は、日本の夏を象徴する食材「ウナギ」について、その神秘的な生態から、驚異的な栄養価、そして、豊かな食文化まで、その魅力と実力を、徹底的に掘り下げてお話ししました。 その細長い体には、3000kmもの長旅を乗り越えるための、生命のエネルギーが、ぎっしりと詰まっています。 私たちが、ウナギを食べて「元気が出る」と感じるのは、その偉大な生命の物語を、丸ごと、私たちの体に取り込んでいるからなのかもしれません。 次にウナギを食べる機会があれば、ぜひ、その一口に込められた、壮大な自然のドラマに、思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
\ 一人で悩んでいませんか?お気軽にご相談ください! /
アンチエイジングアドバイザー Katsuの無料相談窓口
記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます!
「体に良いとは分かっているけど、続けるのが難しい…」 「情報が多すぎて、何から始めたらいいか分からない」 「私のこの不調、どうしたらいいんだろう?」
もしあなたが今、そんな風に感じているなら、ぜひ一度お話を聞かせてください。 日々の食事や運動のこと、サプリメントの選び方、ちょっとした体の悩みまで、どんな些細なことでも構いません。
あなた専用の「かかりつけアドバイザー」として、親身にサポートさせていただきます。
【ご相談までの流れ】
- 下のボタンから、まずはLINEで「友だち追加」してください。
- 追加後、トーク画面からスタンプを一つでも送っていただけると、こちらからご挨拶のメッセージをお送りします。
- その後、あなたのペースでご相談内容をお聞かせください。
もちろん相談は無料です。安心して、下のボタンをタップしてくださいね。
▼公式LINEでKatsuに無料で相談してみる 無料で相談してみる
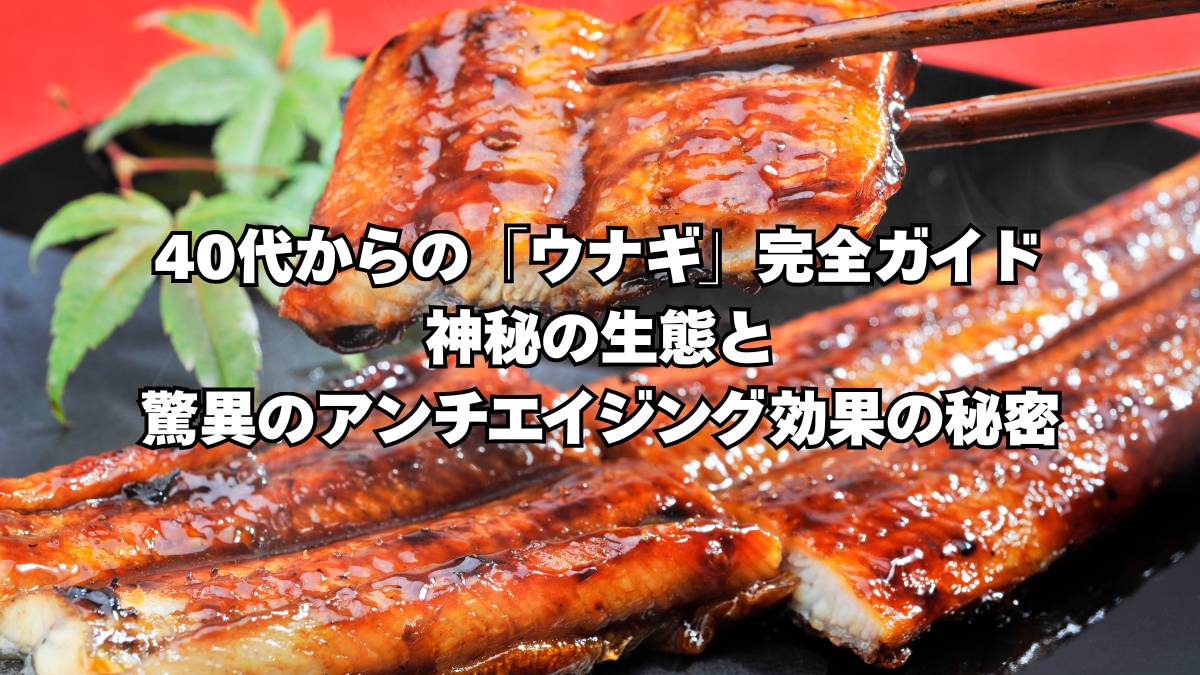
コメント