こんにちは!
アンチエイジングアドバイザーのKatsu(@adviserkatsu)です。
厳しい冬の寒さの中、湯気の立つ鍋料理の中心で、雪のように真っ白な身を輝かせる魚。 淡白でありながら、ほろりとした食感と、上品な旨味で、私たちの心と体を温めてくれる、冬の味覚の代表格、タラ(鱈)。 「鱈」という漢字が、魚へんに「雪」と書くことからも、いかに古くから、冬の魚として日本人に親しまれてきたかが分かりますね。
「タラは、脂肪が少なくてヘルシーな魚」 そんなイメージをお持ちの方は、多いのではないでしょうか。 そのイメージは、もちろん大正解です。 しかし、その淡白な姿の裏に、私たちの体の「解毒」や「抗酸化」といった、アンチエイジングの根幹を支える、非常にパワフルな力が秘められていることは、あまり知られていません。
今回は、そんなタラの奥深い世界を、4つのテーマに沿って、その生態から、科学的に証明された驚くべき栄養価、そして、その魅力を最大限に引き出す究極の食べ方まで、徹底的に掘り下げていきたいと思います。
雪のように白い深海の魚、タラの世界
まず、私たちが食べているタラが、どのような魚なのか、そのプロフィールから見ていきましょう。
・海の「大食漢」、タラ タラの語源には諸説ありますが、その旺盛な食欲から、「たらふく食べる」の「たら」が語源になった、という説が有名です。 その名の通り、タラは非常に貪欲な肉食魚で、大きな口で、自分の体の半分ほどの大きさの魚まで、丸呑みにしてしまうこともある、海の「大食漢」なのです。 主に、水深200~400mほどの、冷たい海の底深くに生息しています。
・日本の食卓を支える「タラ三兄弟」 日本近海で獲れ、私たちが主に口にしているタラには、主に3つの種類がいます。 ・マダラ(真鱈) 単に「タラ」と言えば、このマダラを指すことがほとんどです。体にまだら模様があるのが特徴で、大きいものでは1mを超える、まさにタラの王様。 淡白で、熱を通しても硬くなりにくい、その上質な白身は、鍋物やムニエルなど、様々な料理で楽しまれます。 そして、冬の味覚の王様とも言える、クリーミーで濃厚な「白子(しらこ)」がとれるのも、このマダラです。
・スケトウダラ(介党鱈) マダラよりも、やや細身で、スマートな体つきをしています。 実はこのスケトウダラ、日本の漁獲量が最も多い魚種の一つであり、私たちの食生活を、陰から力強く支えてくれている、非常に重要な存在です。 その身は、かまぼこやちくわ、カニカマといった「練り製品」の主原料である「すり身」に加工されます。 そして、その卵巣を塩漬けにしたものこそが、おにぎりの具の定番「タラコ」であり、それを唐辛子などで味付けしたものが「明太子」なのです。
・コマイ(氷下魚) 北海道の冬の風物詩として知られる、タラの仲間です。 氷の下で漁獲されることから、この名がつきました。 生のまま食べることは少なく、一夜干しなどの干物にして、軽く炙って、マヨネーズと一味唐辛子でいただくのが、定番の食べ方です。
低脂肪だけじゃない!抗酸化物質グルタチオンの力
タラの栄養価を語る上で、まず注目すべきは、その驚くべき「低脂肪・低カロリー・高たんぱく」という、完璧なダイエット食材としてのプロフィールです。 マダラ100gあたりのエネルギーは、わずか72kcal。そして、脂質は、驚きの0.2g。 それでいて、たんぱく質は17.6gと、しっかり摂ることができる。 まさに、ダイエット中や、体調不良時の栄養補給に最適な、究極のヘルシー食材なのです。 しかし、タラの真の力は、それだけではありません。
・最強の抗酸化物質「グルタチオン」 タラの白身には、近年、美容と健康の世界で絶大な注目を集めているグルタチオンという成分が含まれています。 グルタチオンは、グルタミン酸、システイン、グリシンという3つのアミノ酸から成る物質で、私たちの体内の、ほぼ全ての細胞に存在しています。 その最も重要な働きが、強力な「抗酸化作用」と「解毒作用」です。 「マスターアンチオキシダント(抗酸化の司令塔)」とも呼ばれ、ビタミンCやビタミンEといった、他の抗酸化物質をサポートし、その効果を高める働きもあります。 特に、肝臓での解毒作用において、中心的な役割を果たしており、体内に取り込まれた有害物質を、無毒化し、体外へ排出するのを助けてくれます。
・骨の健康を守る「ビタミンD」 タラには、骨の健康に不可欠なビタミンDが豊富に含まれています。 ビタミンDは、腸でのカルシウムの吸収を促進し、骨や歯を丈夫にする、非常に重要なビタミンです。 骨密度が気になり始める、私たち40代以降の世代にとっては、積極的に摂取したい栄養素の筆頭です。
・若返りのビタミン「ビタミンE」 強力な抗酸化作用を持つビタミンEも含まれています。 ビタミンEは、細胞膜の酸化を防ぎ、老化を抑制したり、悪玉コレステロールの酸化を防いで、動脈硬化を予防したりする効果が期待されています。
・肝臓のサポーター「タウリン」 肝機能の向上や、コレステロール値の安定に役立つタウリンも含まれています。
冬の鍋から夏のムニエルまで。一年中タラを楽しむ
淡白でクセのないタラは、どんな調理法や味付けにも、しなやかにマッチする、非常に懐の深い魚です。
・タラの旬は、やっぱり「冬」 マダラの旬は、産卵を控えて、身がふっくらと厚くなる、冬。 この時期のタラは、鍋物(たらちり)で、その上品な旨味を味わうのが最高です。 そして、何よりも、冬の味覚の王様「白子」が楽しめるのも、この時期ならではの特権。 クリーミーで濃厚な白子ポン酢は、まさに至福の味わいです。
・和食の定番料理 ・煮付け 淡白なタラの身に、甘辛い煮汁が染み込んだ煮付けは、ご飯がすすむ、家庭料理の定番です。 ・昆布締め 富山などの郷土料理。昆布の旨味が、タラの淡白な身に、ぎゅっと染み込み、ねっとりとした食感の、絶品の刺身へと昇華させます。
・世界の食卓で愛されるタラ ・ムニエル フレンチの定番。小麦粉をはたいて、バターで香ばしく焼き上げるムニエルは、タラの美味しさを、シンプルかつ最大限に引き出す調理法です。 ・フィッシュ・アンド・チップス イギリスを代表する国民食。この料理に使われる白身魚は、伝統的に、タラが最もポピュラーです。 ・ホイル焼き 野菜やきのこ、バターと一緒に、アルミホイルで包んで蒸し焼きにするホイル焼きは、手軽で、栄養バランスも良い、素晴らしい調理法です。
「タラコ」はマダラの子じゃない?意外なタラの豆知識
最後に、知っていると、タラとの付き合いがもっと楽しくなる、豆知識をいくつかご紹介します。
・「タラコ」と「明太子」の、本当の親 私たちがおにぎりやパスタで、日常的に親しんでいる「タラコ」。 漢字で書くと「鱈子」となるため、当然、マダラの子(卵巣)だと思われがちですが、実は、これは間違いです。 タラコの親は、マダラではなく、スケトウダラなのです。 そして、このタラコを、唐辛子などを使った調味液に漬け込んだものが「明太子」です。 「明太(ミョンテ)」とは、朝鮮語でスケトウダラを意味する言葉なのです。
・「たらふく食べる」の語源 「お腹いっぱい食べる」ことを意味する、この面白い表現。 その語源は、タラの旺盛な食欲にある、と言われています。 大きく裂けた口で、何でも丸呑みにしてしまう、その貪欲な姿から、この言葉が生まれたとされています。
・世界史を動かした魚「干しダラ」 タラは、その脂肪の少なさから、塩漬けにして乾燥させる「干しダラ」という、優れた保存食に加工されてきました。 この干しダラは、中世ヨーロッパにおいて、大航海時代のヴァイキングたちの、長期航海を支える、貴重なたんぱく質源となりました。 また、カトリックの食の戒律(肉食を禁じる期間)における、重要な食材としても、ヨーロッパ全土に広まり、巨大な貿易商品として、時には、国と国との戦争(タラ戦争)の原因にまでなった、まさに「世界史を動かした魚」なのです。
というわけで
今回は、冬の味覚の代表格「タラ」について、その生態から、驚異的な栄養価、そして、豊かな食文化まで、その魅力と実力を、徹底的に掘り下げてお話ししました。 その雪のように白い、淡白な身には、低脂肪・高たんぱくという、ダイエットの味方としての側面に加え、私たちの体の解毒と抗酸化を司る、グルタチオンという、強力なアンチエイジングパワーが秘められていました。 ぜひ、今夜の食卓に、この「究極のジェントル・ヒーラー」を、迎えてみてはいかがでしょうか。
\ 一人で悩んでいませんか?お気軽にご相談ください! /
アンチエイジングアドバイザー Katsuの無料相談窓口
記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます!
「体に良いとは分かっているけど、続けるのが難しい…」 「情報が多すぎて、何から始めたらいいか分からない」 「私のこの不調、どうしたらいいんだろう?」
もしあなたが今、そんな風に感じているなら、ぜひ一度お話を聞かせてください。 日々の食事や運動のこと、サプリメントの選び方、ちょっとした体の悩みまで、どんな些細なことでも構いません。
あなた専用の「かかりつけアドバイザー」として、親身にサポートさせていただきます。
【ご相談までの流れ】
- 下のボタンから、まずはLINEで「友だち追加」してください。
- 追加後、トーク画面からスタンプを一つでも送っていただけると、こちらからご挨拶のメッセージをお送りします。
- その後、あなたのペースでご相談内容をお聞かせください。
もちろん相談は無料です。安心して、下のボタンをタップしてくださいね。
▼公式LINEでKatsuに無料で相談してみる 無料で相談してみる
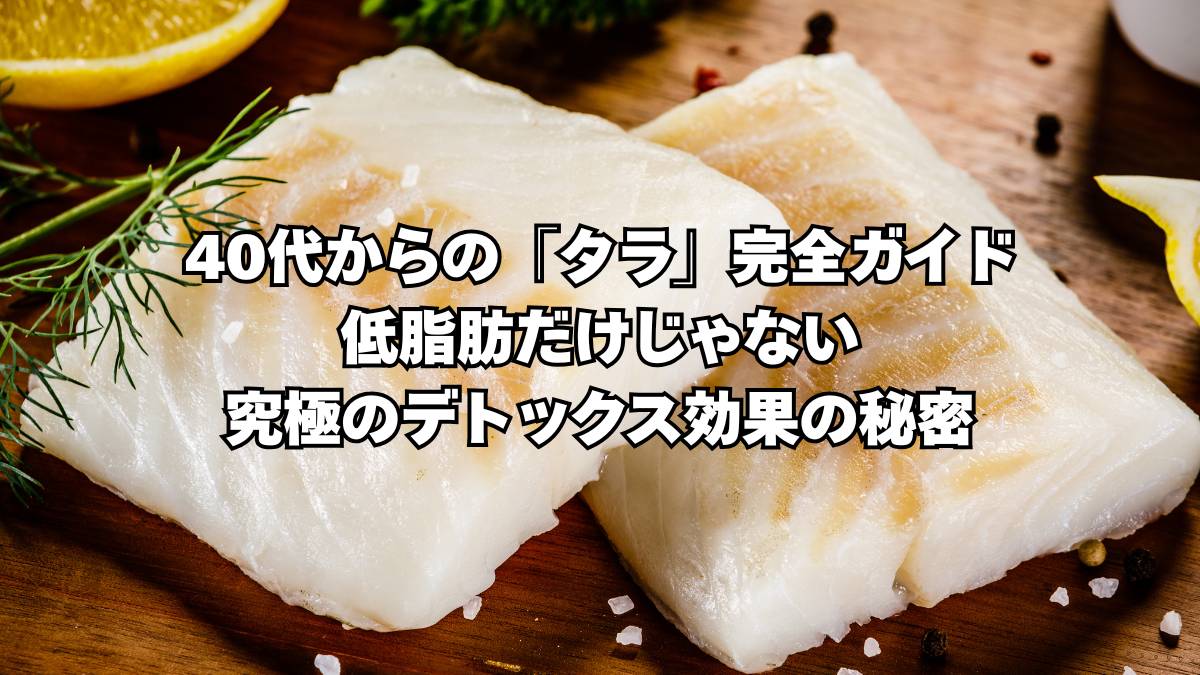
コメント