こんにちは!
アンチエイジングアドバイザーのKatsu(@adviserkatsu)です。
朝食の定番である塩鮭、お弁当を彩るフレーク、お祝いの席に華を添えるお刺身やイクラ…。 私たち日本人にとって、サケ(鮭)は、食卓に最も馴染み深い魚の一つですよね。 その美しいサーモンピンクの身は、美味しさはもちろんのこと、なんとなく「体に良さそう」「美容に良さそう」という、ポジティブなイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そのイメージは、まさに大正解。 サケは、単なる美味しい魚ではありません。 それは、私たちの体を、老化という抗いがたい流れから守ってくれる、「究極のアンチエイジングフィッシュ」とでも言うべき、驚異的なパワーを秘めた、奇跡の食材なのです。
今回は、そんなサケの奥深い世界を、4つのテーマに沿って、その知られざる物語と、科学的に証明された驚くべき栄養価を、徹底的に掘り下げていきたいと思います。
太平洋を旅する偉大な旅人、サケの一生
まず、私たちが食べているサケが、どのような一生を送り、私たちの食卓にやってくるのか。その壮大で、少し切ない物語から見ていきましょう。
・サケとマスの、あいまいな関係 本題に入る前に、少しだけ言葉の整理をさせてください。私たちは、普段「サケ」や「マス」という言葉を何気なく使っていますが、この二つの境界線は、実は非常にあいまいです。 生物学的には、どちらも同じサケ科サケ属の魚であり、明確な分類上の違いはありません。 一般的には、海に下って大きく成長し、生まれた川に帰ってくるものを「サケ」、一生を川や湖で過ごすものを「マス」と呼ぶことが多いですが、例外も多く、その区別は、科学的というよりは、文化的な側面が強いのが実情です。 例えば、海で養殖されたニジマスが「サーモントラウト」という名前で売られているのも、その一例ですね。
・母なる川を目指す、壮絶な旅 サケの生態で、最も私たちの心を打つのが、「母川回帰(ぼせんかいき)」という、その驚くべき習性です。 日本の川で生まれたサケの稚魚は、数ヶ月を川で過ごした後、大海原へと旅立ちます。 アリューシャン列島やベーリング海といった、遥か北の海まで、数千キロにも及ぶ大回遊を行い、そこで豊富なエサを食べて、3~5年の歳月をかけて、大きく成長します。 そして、産卵の時期が来ると、驚くべきことに、彼らは、自分が生まれた川の「匂い」を頼りに、再び数千キロの過酷な旅を経て、故郷の川へと寸分たがわず帰ってくるのです。 川に帰ってきたサケは、一切エサを食べることなく、最後の力を振り絞って、激流を遡上し、産卵を終えると、その壮絶な一生を終えます。 私たちが「秋鮭」として味わっているのは、この、故郷の川に帰ってきた、生命の全てを凝縮した、神々しいまでの姿なのです。
・日本の食卓を彩る、サケの仲間たち 日本で食べられているサケには、いくつかの種類があります。
・シロザケ 日本で最も一般的に漁獲されるサケで、「秋鮭」とも呼ばれます。脂肪は比較的少なめで、さっぱりとした味わいが特徴です。塩焼きや石狩鍋、ちゃんちゃん焼きなど、幅広い料理で親しまれています。
・ギンザケ 現在、国内で流通しているものの多くが、チリなどからの養殖ものです。シロザケよりも脂がのっており、お弁当の切り身など、普段使いのサケとして人気です。
・ベニザケ その名の通り、非常に鮮やかな赤い身が特徴です。この赤色は、後述するアスタキサンチンが豊富な証。濃厚な味わいで、塩蔵品の「紅鮭」として、根強い人気を誇ります。
・キングサーモン(マスノスケ) 名前の通り、サケの王様。最も大きく成長し、脂のりも最高級。刺身やステーキで楽しまれる、特別なご馳走です。
赤い身の秘密、アスタキサンチンとスーパー栄養素たち
サケの栄養価を語る上で、絶対に外すことのできない、最大の特徴。 それは、他の魚にはない、あの美しいサーモンピンクの身に秘められた、奇跡の栄養素の存在です。
・最強の抗酸化物質「アスタキサンチン」 サケの身や卵(イクラ)が赤いのは、アスタキサンチンという、天然の赤い色素成分によるものです。 これは、サケが、オキアミやエビ、カニといった、アスタキサンチンを豊富に含む甲殻類をエサにしているために、その体に蓄積されるのです。 このアスタキサンチンこそが、サケを「究極のアンチエイジングフィッシュ」たらしめている、最大の秘密兵器です。 アスタキサンチンは、数ある抗酸化物質の中でも、その抗酸化力は、ビタミンEの数百倍~1000倍とも言われるほど、桁違いに強力なのです。 私たちの体をサビつかせ、老化による免疫力の低下や、動脈硬化といった、あらゆる不調の原因となる「活性酸素」を、無力化してくれる、最強の味方です。 さらに、アスタキサンチンは、脳や目の奥まで届くことができる、数少ない抗酸化物質の一つとしても知られています。
・脳と血管の守護神「EPA・DHA」 サケは、アジやサバと並ぶ、青魚の仲間でもあります。 その脂には、不飽和脂肪酸であるEPAとDHAが豊富に含まれています。 100gあたりの含有量は、シロザケでもEPAが240mg、DHAが460mg。脂がのった養殖のサーモンなどでは、さらに多くの量が含まれます。 血液をサラサラにし、血管系の病気の予防に役立つEPAと、脳の機能をサポートするDHA。これらの健康効果は、もはや説明不要でしょう。
・骨の建築を指揮する「ビタミンD」 サケには、骨の健康に不可欠なビタミンDが、非常に豊富に含まれています。 ビタミンDは、食事から摂ったカルシウムの吸収を助ける働きがあり、骨粗しょう症が気になる、私たち40代以降の世代にとっては、絶対に不足させてはならない栄養素です。
・その他、脇を固める栄養素たち 筋肉の材料となる良質なたんぱく質(約22.3g)、エネルギー代謝を助けるビタミンB群(B1, B12など)、そして、皮やイクラに含まれるビタミンAやビタミンEなど、まさに栄養素のオールスターチームと言えるでしょう。
朝食の定番からご馳走まで!サケを丸ごと味わい尽くす食べ方
サケの素晴らしい栄養を、余すことなく、そして美味しくいただくための、食べ方のヒントをご紹介します。
・サケの旬はいつ? サケの種類によって、旬は異なります。 日本で獲れる天然のシロザケ(秋鮭)の旬は、その名の通り、産卵のために川に帰ってくる秋です。この時期のものは、脂は少し落ちていますが、卵(筋子やイクラ)を抱えているのが特徴です。 一方、海外産の天然ベニザケなどは、春から夏にかけて旬を迎えます。 ギンザケやアトランティックサーモンといった養殖ものは、一年を通して、安定して脂がのった状態で流通しています。
・骨の健康を意識した、最高の食べ合わせ サケが、骨の健康に重要なビタミンDを豊富に含むことを考えると、最高のパートナーは、やはり「カルシウム」です。 チーズや牛乳、ヨーグルトといった乳製品をはじめ、小松菜や豆腐など、カルシウムを含む食材と合わせて食べることで、栄養効果がぐんと上がります。 例えば、 ・サーモンとクリームチーズのベーグル ・鮭とほうれん草のクリームパスタやグラタン ・鮭フレークとチーズを乗せたトースト これらは、味の相性が良いだけでなく、栄養学的にも、非常に理にかなった、素晴らしい組み合わせなのです。
・日本の食卓を彩る、定番の鮭料理 ・塩焼き 日本の朝食の原風景とも言える、最もシンプルな食べ方です。パリッと焼けた皮と、ふっくらとした身のコントラストが、食欲をそそります。 ・ちゃんちゃん焼き、石狩鍋 北海道の郷土料理です。鮭と、たっぷりの野菜を、味噌ベースの味付けで楽しむこれらの料理は、栄養バランスの観点からも、非常に優れています。 ・ルイベ アイヌ民族の伝統的な料理で、一度冷凍した生のサケを、半解凍の状態で薄切りにして食べる、天然のフローズンサーモンです。冷凍することで、寄生虫の心配なく、安全に食べられるという、先人の知恵が生きています。
イクラは体に良い?意外と知らないサケの雑学
最後に、知っていると、サケとの付き合いがもっと楽しくなる、豆知識をいくつかご紹介します。
・「皮」と「イクラ」は、栄養の塊 焼き魚の「皮は食べない」という方もいらっしゃいますが、それは、あまりにも、もったいないことです。 サケの皮は、香ばしく焼くと非常においしいだけでなく、コラーゲンや、EPA・DHAといった良質な脂質が豊富に含まれています。 そして、キラキラと輝く宝石「イクラ」。これは、次世代の命を生み出すための、栄養のカプセルです。 親であるサケの身以上に、DHAやEPA、そして、ビタミンA、Eといった、抗酸化ビタミンが凝縮されています。
・サケは、実は「白身魚」 前回の記事でも少し触れましたが、あの美しいサーモンピンクの色から、サケは「赤身魚」だと思われがちですが、実は、筋肉の性質から分類すると「白身魚」の仲間です。 身の赤色は、筋肉色素のミオグロビンによるものではなく、エサである甲殻類由来の、抗酸化物質アスタキサンチンによるものなのです。
・サステナブルな選択を 近年、天然サケの資源保護や、養殖における環境への配慮が、世界的な関心事となっています。 私たちが、この素晴らしい食材を、未来永続的に楽しむためには、消費者である私たち自身が、賢い選択をすることが求められます。 例えば、養殖のサケを選ぶ際には「ASC認証」、天然のサケを選ぶ際には「MSC認証(海のエコラベル)」といった、環境や社会に配慮した水産物であることを示す認証ラベルを、参考にするのも良いでしょう。
というわけで
今回は、私たちの食卓に最も身近な魚の一つ「サケ」について、その壮大な一生の物語から、驚異的なアンチエイジング効果、そして、豊かな食文化まで、その魅力と実力を、徹底的に掘り下げてお話ししました。 その美しい赤い身には、老化という、抗いがたい自然の摂理に、力強く立ち向かうための、アスタキサンチンという、自然界からの最高の贈り物が秘められています。 ぜひ、今夜の食卓に、この「究極のアンチエイジングフィッシュ」を、迎えてみてはいかがでしょうか。
\ 一人で悩んでいませんか?お気軽にご相談ください! /
アンチエイジングアドバイザー Katsuの無料相談窓口
記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます!
「体に良いとは分かっているけど、続けるのが難しい…」 「情報が多すぎて、何から始めたらいいか分からない」 「私のこの不調、どうしたらいいんだろう?」
もしあなたが今、そんな風に感じているなら、ぜひ一度お話を聞かせてください。 日々の食事や運動のこと、サプリメントの選び方、ちょっとした体の悩みまで、どんな些細なことでも構いません。
あなた専用の「かかりつけアドバイザー」として、親身にサポートさせていただきます。
【ご相談までの流れ】
- 下のボタンから、まずはLINEで「友だち追加」してください。
- 追加後、トーク画面からスタンプを一つでも送っていただけると、こちらからご挨拶のメッセージをお送りします。
- その後、あなたのペースでご相談内容をお聞かせください。
もちろん相談は無料です。安心して、下のボタンをタップしてくださいね。
▼公式LINEでKatsuに無料で相談してみる 無料で相談してみる
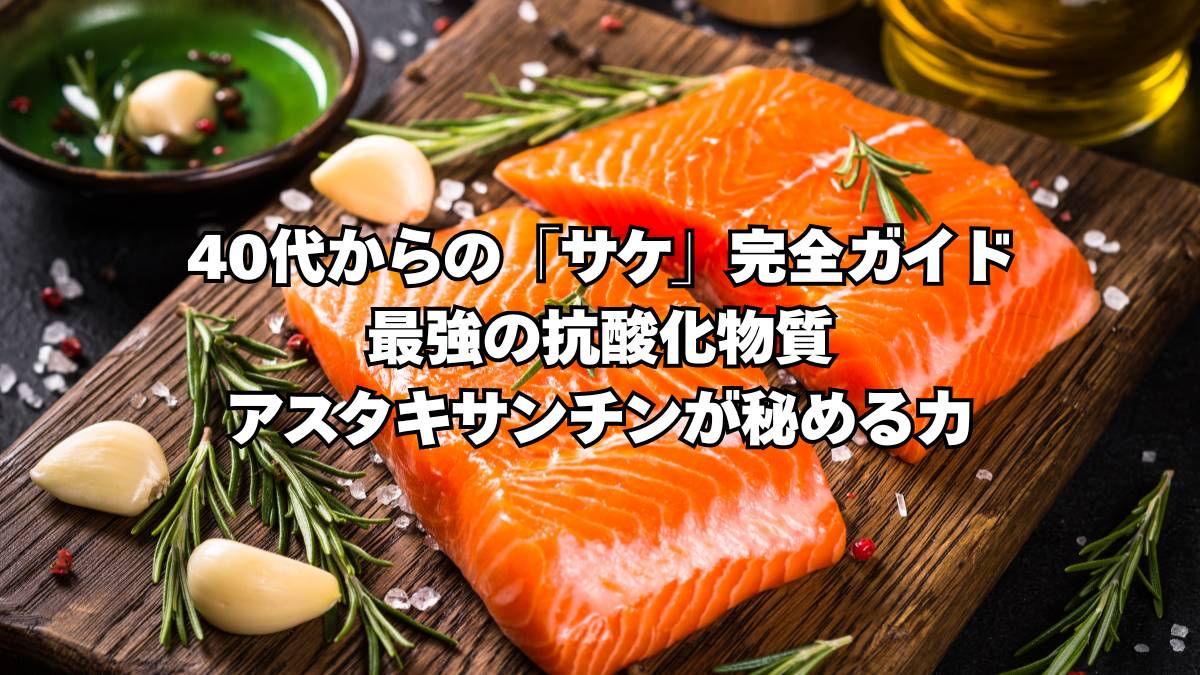
コメント