こんにちは!
アンチエイジングアドバイザーのKatsu(@adviserkatsu)です。
塩焼き、フライ、お刺身、なめろう…。 日本の食卓に、これほどまでに深く、そして多彩な形で浸透している魚が、他にあるでしょうか。 今回、私たちがその魅力に迫るのは、まさに「食卓の定番」の名にふさわしい魚、アジ(鯵)です。
「アジは、美味しくて、手頃で、食べやすい魚」 多くの方が、そんな親しみやすいイメージをお持ちだと思います。 しかし、その日常に溶け込んだ姿の裏に、特に私たち40代以降の健康を、多方面から力強くサポートしてくれる、驚くべき栄養パワーが秘められていることをご存知でしょうか?
今回は、そんなアジの知られざる実力を、4つのテーマに沿って、深く、そして徹底的に掘り下げていきたいと思います。 この記事を読み終える頃には、スーパーの鮮魚コーナーで輝く一匹のアジが、もはや単なる「おかず」ではなく、あなたの未来の健康を守る「最高のパートナー」に見えてくるはずです。
項目1:アジってどんな魚?
「アジ」と一言で言っても、実は非常に多くの種類がおり、その生態も様々です。まずは、私たちが愛するこの魚の「プロフィール」から見ていきましょう。
・「味」が良いから「アジ」 アジという名前の由来には諸説ありますが、最も有名なのが、そのあまりの美味しさから「味」が良い魚、という意味で「アジ」と名付けられた、という説です。古くから、その味が日本人の舌を魅了してきたことが伺える、素敵な名前ですよね。
・アジの代表格「マアジ」 生物学的には、スズキ目アジ科に属する魚たちの総称ですが、私たちが日本で一般的に「アジ」と呼んでいるのは、その中でも代表格であるマアジ(真鯵)を指します。 体の中央に、硬くて鋭いトゲのような鱗「ぜんご(または、ぜいご)」が並んでいるのが、マアジの最大の特徴です。
・回遊する「クロアジ」と、根付きの「キアジ」 同じマアジでも、その生態によって、実は2つのタイプに分けられます。 一つは、外洋を広く回遊する、黒っぽい見た目の「クロアジ」。運動量が多く、身が引き締まっているのが特徴です。 もう一つは、沿岸の岩礁などに定住する、黄色みを帯びた「キアジ」または「根付きアジ」です。回遊しない分、エサを豊富に食べており、脂がのって丸々と太っているのが特徴で、高級ブランドアジとして扱われることも少なくありません。
・アジの仲間たち(シマアジ、ムロアジなど) アジ科には、他にも個性豊かな仲間がいます。 「シマアジ」は、その美しい姿と、上品な脂のりで知られる、刺身用の最高級魚です。マアジとは属が異なりますが、アジ科のスター選手と言えるでしょう。 「ムロアジ」は、伊豆諸島の特産品である、独特の風味を持つ干物「くさや」の原料として、あまりにも有名です。
このように、アジは、非常に多様な個性を持つ、奥深い魚なのです。
項目2:アジに含まれる栄養素とその効果
アジが「日常のスーパーフード」と呼ばれる所以は、そのバランスの取れた、驚くべき栄養価にあります。100gあたりに含まれる主な栄養素とその効果を見ていきましょう。
・スター選手「EPA」と「DHA」 アジは、サバやイワシと並ぶ、青背魚の代表格。その最大の特徴は、脂質に含まれる不飽和脂肪酸、DHAとEPAが、非常に豊富であることです。 ・EPA(エイコサペンタエン酸):血液と血管の守護神 EPAは、血液をサラサラにし、血栓の予防に関わります。また、悪玉コレステロール値や血圧の上昇を抑える働きもあると言われ、動脈硬化や心筋梗塞といった、生活習慣病の予防に、絶大な効果を発揮します。 ・DHA(ドコサヘキサエン酸):脳と神経の最高の材料 DHAは、私たちの脳の機能に重要な役割を果たします。脳の神経細胞の主成分であり、記憶力や学習能力の維持に不可欠です。40代以降に気になる、認知機能の低下を予防する上でも、積極的に摂りたい栄養素です。
・体の土台を作る「良質なたんぱく質」(約19.7g) アジは、筋肉や皮膚、髪の毛の材料となる、良質なたんぱく質も豊富です。 40代以降、何もしなければ、私たちの筋肉量は、年々減少していきます。筋肉量の低下は、基礎代謝の低下を招き、「太りやすく、痩せにくい体」の原因となります。 アジを食べることは、この筋肉の衰えを防ぎ、若々しい体を維持するための、最も美味しく、そして効果的な方法の一つなのです。
・骨の健康を守る「カルシウム」と「ビタミンD」 アジには、骨の材料となるカルシウムと、そのカルシウムの吸収を助けるビタミンDの両方が、バランス良く含まれています。 この2つの栄養素は、チームで働くことで、骨粗しょう症の予防に、非常に効果的に作用します。特に、後述するように、骨ごと食べる工夫をすることで、その効果を最大限に引き出すことができます。
・元気の源「ビタミンB群」 エネルギー代謝を助けるビタミンB2をはじめ、体の調子を整えるビタミンB群も含まれています。
・肝臓のサポーター「タウリン」 栄養ドリンクの成分としてもおなじみのタウリンも含まれており、肝機能のサポートや、血圧の安定に役立ちます。
項目3:アジの美味しい食べ方と旬について
アジの栄養を、余すことなく、そして美味しくいただくための、食べ方のヒントをご紹介します。
・アジの「旬」はいつ? アジは、ほぼ一年中市場に出回っていますが、その味が最も良くなる「旬」は、一般的に、初夏から夏(5月~8月頃)と言われています。 この時期のアジは、産卵を控えて、体に栄養と脂をたっぷりと蓄えているため、ふっくらと肉厚で、EPAやDHAの含有量もピークに達します。
・食べ方の多様性 アジの素晴らしいところは、和食から洋食まで、どんな料理にも変身できる、その調理法の多様性にあります。 新鮮なものは、お刺身やタタキ、千葉の郷土料理である「なめろう」などで、そのものの味を楽しむのが最高です。 定番の塩焼きや、子供も大好きなアジフライはもちろん、ムニエルやマリネといった、洋風の調理法にも、驚くほどよく合います。
・骨ごと食べて、カルシウムを丸ごといただく アジの栄養を、骨の髄まで、文字通り「丸ごと」いただくための、最高の調理法。それが、小アジを使った料理です。 小アジを、頭から尾まで丸ごと、低温でじっくりと二度揚げすれば、骨までサクサクと食べられる、絶品の唐揚げになります。 これを、お酢や香味野菜と共に漬け込む「南蛮漬け」は、カルシウムの吸収を、お酢がさらに助けてくれる、まさに骨の健康のための、理想的な一品です。
項目4:アジについての豆知識
最後に、知っていると、アジとの付き合いが、もっと楽しく、もっと上手になる豆知識をいくつかご紹介します。
・アジを買ってきたら、まず最初にすべきこと アジは、その内臓が非常に傷みやすい魚です。 内臓には、強力な消化酵素が含まれているため、そのままにしておくと、その酵素が、自身の身まで溶かし始め、鮮度が一気に落ちてしまいます。 丸ごと一匹買ってきた場合は、なるべく早く、エラと内臓を取り除くこと。これが、アジを美味しく食べるための、鉄則です。 処理した後は、キッチンペーパーなどで、水気をしっかりと拭き取ってから、冷蔵庫で保存しましょう。
・「ぜんご(ぜいご)」の正体と、簡単な取り方 アジの体の側面にある、トゲトゲとした硬い鱗。これが「ぜんご」です。 これは、外敵から身を守るための鎧の役割や、水中での体の安定を保つ役割があると言われています。 食べられない部分なので、調理の前に取り除く必要がありますが、包丁の刃を、尾の付け根から頭に向かって、ギコギコと動かすように入れるだけで、意外と簡単に取ることができます。
・新鮮なアジの見分け方 スーパーで、最高のパートナーを選ぶための、目利きのポイントです。 ・目が黒く澄んでいること ・エラが鮮やかな紅色をしていること ・体にハリがあり、持った時に、お腹がだらんと垂れないこと ・皮に、ツヤと輝きがあること これらの点をチェックすれば、あなたも今日から、アジの目利きです。
というわけで
今回は、私たちの食卓の定番魚「アジ」について、その知られざる栄養価と、健康効果、そして、その魅力を最大限に引き出すための、奥深い世界を探求しました。 手頃な価格で、一年中手に入り、どんな料理にも変身してくれる、親しみやすい存在。 その小さな体には、私たちの脳と血管を、そして骨の健康までもを守ってくれる、計り知れないほどのパワーが、ぎっしりと詰まっているのです。
ぜひ、今夜の食卓に、この「日常のスーパーフードの王様」を、迎えてみてはいかがでしょうか。
\ 一人で悩んでいませんか?お気軽にご相談ください! /
アンチエイジングアドバイザー Katsuの無料相談窓口
記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます!
「体に良いとは分かっているけど、続けるのが難しい…」 「情報が多すぎて、何から始めたらいいか分からない」 「私のこの不調、どうしたらいいんだろう?」
もしあなたが今、そんな風に感じているなら、ぜひ一度お話を聞かせてください。 日々の食事や運動のこと、サプリメントの選び方、ちょっとした体の悩みまで、どんな些細なことでも構いません。
あなた専用の「かかりつけアドバイザー」として、親身にサポートさせていただきます。
【ご相談までの流れ】
- 下のボタンから、まずはLINEで「友だち追加」してください。
- 追加後、トーク画面からスタンプを一つでも送っていただけると、こちらからご挨拶のメッセージをお送りします。
- その後、あなたのペースでご相談内容をお聞かせください。
もちろん相談は無料です。安心して、下のボタンをタップしてくださいね。
▼公式LINEでKatsuに無料で相談してみる 無料で相談してみる
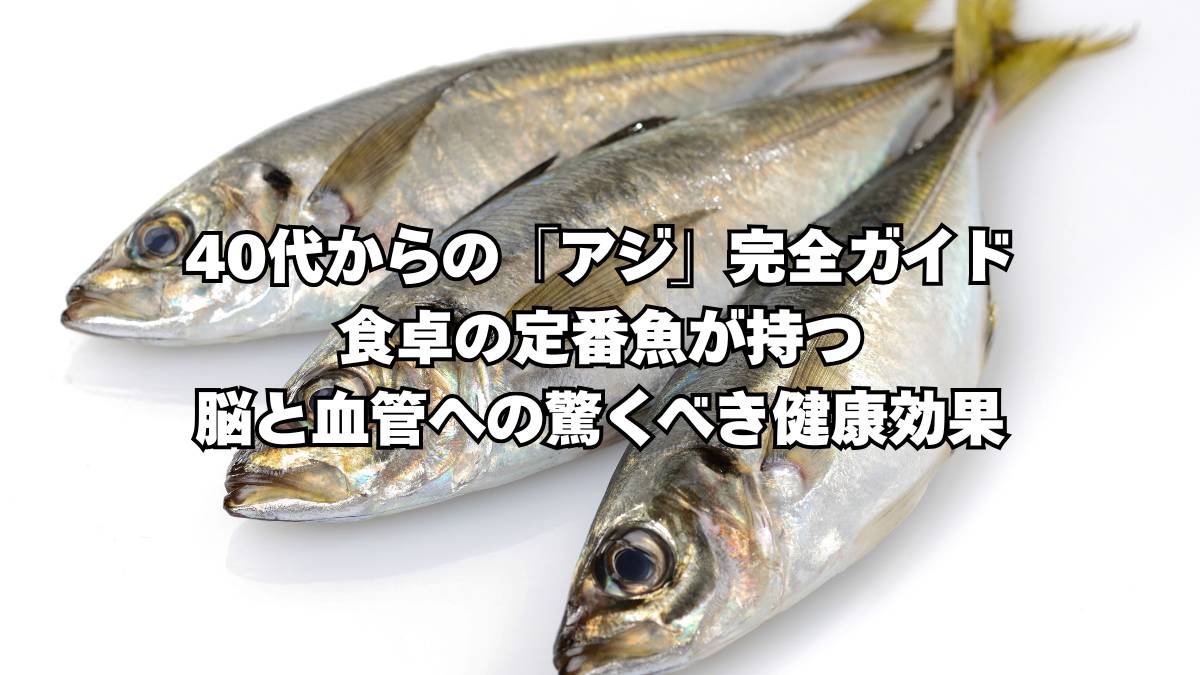
コメント