こんにちは
アンチエイジングアドバイザーのKatsu(Instagramはこちら)です
今回は「塩素(ナトリウム・クロール)」について、体にどんな働きをしているのか、どんな食品に多く含まれるのかなど、実生活で本当に役立つ情報をできるだけ分かりやすく、しっかり深掘りして解説します。
塩素とは?体内での役割
塩素は、体内に約150gも含まれる「多量ミネラル」のひとつです。
このほとんどが「細胞外液」に存在しており、ナトリウムとともに“食塩”として摂取するのが一般的です。
体の中では、ナトリウムイオンとクロールイオンの形で存在していて、
電解質バランス(イオンバランス)を維持したり、体液の量や質を調整するのに欠かせません。
体液の浸透圧や性質を調整する
塩素は、細胞外液(血液やリンパ液など)を構成する主要な成分です。
細胞の内と外で水分や栄養素、老廃物などのやりとりがスムーズにできるよう、
「浸透圧」を調整する役割があります。
さらに、体液の酸性・アルカリ性のバランスを整える働きもあり、
体内のpHバランスが崩れないように、絶えず調整をしています。
この機能が乱れると、脱水やむくみ、高血圧などの原因になることもあります。
消化を促進する
塩素は、体の中で「塩酸」に変化します。
この塩酸が「胃酸」の主成分となり、食べ物をしっかり分解・消化するのに不可欠です。
また、消化酵素がしっかり働くためにも、適度な塩素が必要です。
食事をするときに「胃液が出てこない」と、食べたものがうまく消化されず、
消化不良やガス腹、胃もたれ、ビタミンやミネラルの吸収不良などに繋がることもあります。
どんな食品に多く含まれている?
塩素は、ほぼ「食塩」として摂取しています。
しお、しょうゆ、みそ、漬物、加工食品などの調味料・保存食品・塩味の強い食品にはたっぷり含まれています。
特に日本人は、味噌汁・醤油・漬物・加工品(ハム、ソーセージ、カップ麺など)から、
必要量をはるかに超えて塩分(=塩素)を摂っている場合が多いです。
塩素の摂取と健康リスク
塩素は生きていく上で不可欠ですが、現代の日本人は摂りすぎに要注意です。
体に必要な摂取量は1日約2g程度(食塩換算で5gほど)と言われていますが、
実際には平均して1日8〜10g(食塩換算)の摂取になっています。
この摂りすぎが高血圧、腎臓病、心臓病、脳卒中、骨粗しょう症など生活習慣病のリスクを大きく高めることが、
世界中の大規模研究で証明されています。
また、腎臓や心臓が弱い方、高齢者、妊婦さんは特に“減塩”を心がけることが勧められています。
摂りすぎ・不足のサイン
塩素が不足することは、通常の食事ではほぼありません。
ごくまれに極端な低塩分ダイエットや長期間の下痢・嘔吐・発汗で不足することがありますが、
多くの場合は「摂りすぎ」の方が問題になります。
摂りすぎのサインとしては、「むくみ」「血圧上昇」「のどが渇く」「夜間頻尿」などがあります。
一方、不足すると「脱水症状」「筋肉のけいれん」「食欲不振」「意識障害」など、深刻な症状を招くことがあります。
塩素と上手につき合うコツ
- できるだけ「薄味」「減塩調味料」を活用する
- 加工食品やインスタント食品を控え、素材の味を生かす調理を心がける
- 漬物・みそ汁・ラーメン・お惣菜などの“ダブル摂取”に注意
- 外食やテイクアウト時はスープを残す、ソースやドレッシングを控える
- 夏場や運動時には発汗分の塩分補給も必要
日常のちょっとした工夫で、「摂りすぎ」を防ぎつつ、必要な分だけしっかり摂ることが大切です。
まとめ
塩素は私たちの命を支えるミネラルですが、摂りすぎが深刻な健康リスクに直結します。
「美味しい」「クセになる」塩味も、健康長寿のためにはちょっと意識してコントロールしたいですね。
減塩を意識しながらも、
夏や運動時など汗をたくさんかいたときは適度な塩分補給を忘れずに。
体のバランスを保つために、「ちょうどよい量」を目指しましょう。
記事を最後まで読んでいただきありがとうございました
美容・健康・アンチエイジングに関する無料相談は随時受け付けております
いつでもお気軽にご相談ください!
無料相談はこちら(公式LINE)→ https://lin.ee/JtvKlEW
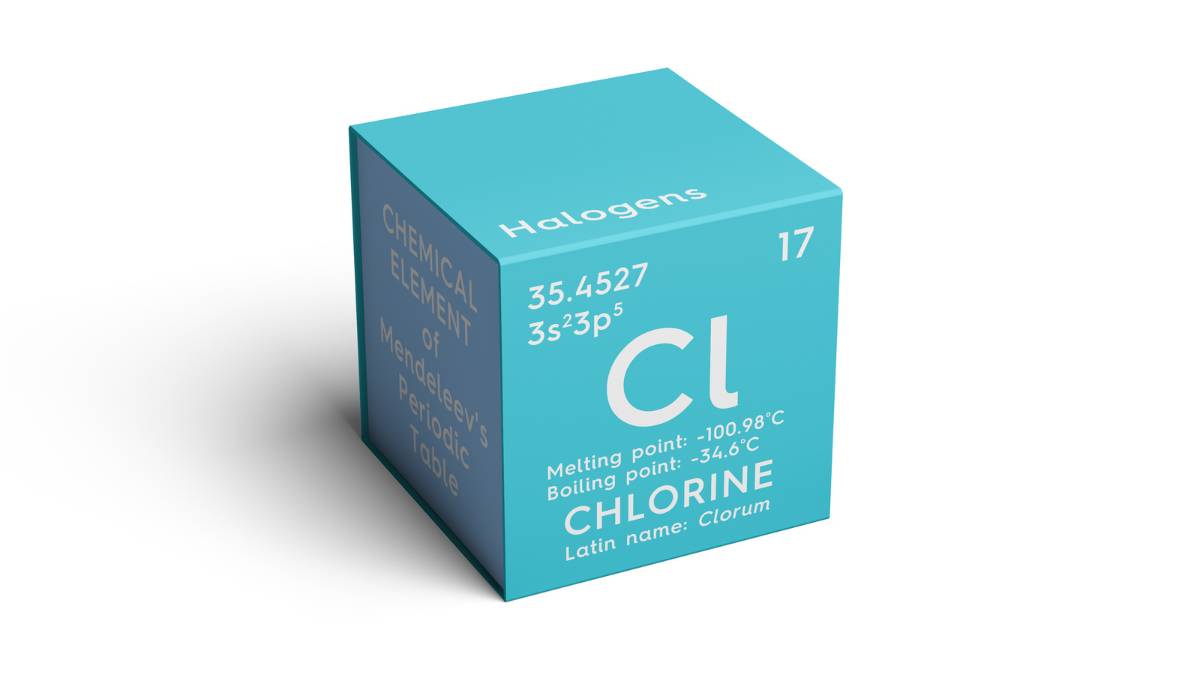
コメント