こんにちは!
アンチエイジングアドバイザーのKatsu(@adviserkatsu)です。
豚の生姜焼き、とんかつ、豚汁、角煮…。 日本の食卓に、これほどまでに深く、そして多彩な形で溶け込み、私たちの「元気」を支えてくれている食材が、他にあるでしょうか。 豚肉は、手頃な価格と、どんな調理法にも応える懐の深さで、牛肉と並び、日々の食卓に欠かせない、大切なパートナーですよね。
しかし、その一方で、牛肉が「高級品」としての華やかさを持つのに対し、豚肉には、どこか「庶民的」で、「脂が多い」というイメージが、付きまとっていないでしょうか。 「疲れている時は、豚肉がいいらしい」と聞きつつも、バラ肉などの脂肪分を目にして、「やっぱり太るかな…」と、少し躊躇してしまう…。 そんな経験を持つ40代の方も、多いかもしれません。
もし、その「脂が多い」という側面ばかりが強調され、豚肉が持つ、他の肉を圧倒するほどの、驚異的な「健康パワー」が見過ごされているとしたら、それは、あまりにも、もったいない話です。
今回は、そんな豚肉の奥深い世界を、4つのテーマに沿って、その知られざる歴史から、科学的に証明された驚くべき栄養価、そして、その力を最大限に引き出す究極の食べ方まで、私の全力を尽くして、徹底的に掘り下げていきたいと思います。
世界が愛する万能食材 豚肉の知られざる歴史と品種
まず、牛肉以上に深く、世界中の食文化に根付いている「豚」という家畜のプロフィールから見ていきましょう。
・豚は「森の掃除屋」だった? 豚の家畜化は、犬に次いで古く、約1万年前には、既に始まっていたと言われています。 元となったのは、猪(イノシシ)です。 豚は、雑食性で、どんなものでも食べ、成長が速く、一度にたくさんの子供を産む、という特徴を持っています。 古代の人々にとって、豚は、人間の食べ残しや森の木の実などを食べて、自ら高品質な肉や脂肪に変えてくれる、非常に効率の良い、貴重な食糧源でした。 特に、森林地帯が多いヨーロッパや中国では、豚は「歩く貯金箱」さながらの存在だったのです。
・日本人は、豚を食べていなかった? 牛肉と同じく、仏教の影響下にあった日本では、豚肉食も、長い間タブーとされてきました。 本格的に豚肉食が広まるのも、やはり明治維新以降のこと。 特に、安価で栄養価が高い豚肉は、軍隊の食糧として注目され、それが除隊した兵士たちによって全国に広まり、「とんかつ」や「カレー」といった、日本の国民食とも言える料理を生み出していきました。
・黒豚はなぜ美味しい? ブランド豚の世界 現在、日本国内で飼育されている豚の9割以上は、LWD系と呼ばれる「ランドレース種(L)」「大ヨークシャー種(W)」「デュロック種(D)」の3品種を掛け合わせた、効率よく大きな肉を生産する品種です。 しかし、近年、効率よりも「味わい」を追求した、多種多様な「ブランド豚」が、人気を博しています。 ・黒豚(バークシャー種) 鹿児島県産が特に有名ですね。一般的な白豚に比べて、成長が遅く、体も小さいですが、その肉質は、きめ細かく、脂肪に甘みがあり、保水性(旨味を逃しにくい)が高いのが特徴です。 その美味しさの秘密は、脂肪の「融点(溶ける温度)」の高さにもあります。一般的な豚の脂肪が33~38℃で溶けるのに対し、黒豚は38~40℃と高め。このため、食べた時にべとつかず、さっぱりとした後味を生み出します。 ・イベリコ豚(スペイン) スペイン原産の黒豚。特に、ドングリを食べて育った最高ランクの「ベジョータ」は、その肉質や脂肪が、オリーブオイルに近い成分構成(オレイン酸豊富)になると言われ、世界中の美食家を虜にしています。 ・あぐー豚(沖縄) 沖縄古来の島豚。成長は非常にゆっくりですが、コレステロール値が低く、旨味成分であるグルタミン酸が豊富で、脂肪に、とろけるような甘みがあるのが特徴です。
牛肉を凌駕する! 疲労回復ビタミンB1の驚異的な力
牛肉が「鉄」の王様だとしたら、豚肉は、間違いなく「ビタミンB1」の王様です。 この一点において、豚肉は、他のあらゆる食材の追随を許さない、圧倒的な価値を持っています。
・ビタミンB1(糖質の代謝を司る、元気の源) 豚肉の最大の特徴は、このビタミンB1の含有量が、牛肉とは段違いであることです。 (画像:牛肉ロース 0.08mg程度に対し、豚肩ロース 0.63mg) その差は、部位にもよりますが、なんと5倍~10倍にも達します。全食品の中でも、トップクラスの含有量です。 ビタミンB1は、私たちが食べたご飯やパン、麺類といった「糖質」を、体(特に脳や神経)のエネルギーに変える際に、絶対に欠かせない「着火剤(補酵素)」の役割を果たします。 もし、ビタミンB1が不足した状態で、糖質ばかりを摂っていると、糖質はエネルギーになれず、乳酸などの疲労物質として体内に蓄積してしまいます。 これが、慢性的な疲労感や、倦怠感、集中力の低下、イライラといった、原因不明の不調の正体です。 さらに、糖質がエネルギーに使われない分は、そのまま体脂肪として蓄積されてしまいます。 つまり、ビタミンB1が不足すると、私たちは「疲れやすく、太りやすい」という、最悪のスパイラルに陥ってしまうのです。 豚肉を食べることは、この糖質の代謝エンジンを、フル回転させるための、最強のカンフル剤となるのです。 この働きこそが、豚肉が「疲労回復」に効くとされる、最大の理由です。 また、エネルギー産生がスムーズに行われることは、精神的な安定にも繋がり、ストレス軽減にも役立つと期待されています。
・ナイアシン(ビタミンB3) 豚肉には、ビタミンB群の仲間であるナイアシンも豊富です。 (画像:7.0mgNE) ナイアシンは、糖質や脂質、たんぱく質の、全ての代謝に関わる、非常に重要なビタミンです。 また、皮膚や粘膜の健康維持、神経機能の正常化、さらにはエネルギー産生そのものに深く関わるため、ストレスの軽減効果も期待されています。
・たんぱく質(美しい肌と筋肉の源) もちろん、豚肉も牛肉同様、良質なたんぱく質の塊です。 (画像:17.1g) 美しい肌や髪、そして、衰えさせたくない筋肉を維持するためには、必要不可欠です。
・脂質についての真実(オレイン酸) 豚肉の脂質は、確かに牛肉に比べて飽和脂肪酸(ステアリン酸など)も多い傾向にありますが、同時に、不飽和脂肪酸であるオレイン酸も多く含んでいるのが特徴です。 オレイン酸は、オリーブオイルの主成分としても知られ、悪玉(LDL)コレステロールを下げる働きがあるとされる、良質な脂肪酸です。 豚肉の脂肪は、不飽和脂肪酸の中では酸化されにくいという特徴があり、一概に「体に悪い脂」と決めつけることはできません。大切なのは、部位を選んで、量をコントロールすることです。
脂身と赤身の使い分け! 豚肉のポテンシャルを120%引き出す食べ方
豚肉は、牛肉以上に「部位」によって、脂肪の量やカロリーが劇的に異なります。 (画像:ヒレ→もも→ロース→ばらの順で増えていく) この個性を理解し、その日の体調や目的によって使い分けることが、豚肉と賢く付き合う最大の秘訣です。
・高脂質な部位(コクと旨味の源) ・ばら(バラ)肉 豚のお腹まわりの肉で、赤身と脂肪が美しい三層肉になっています。 脂質の量が最も多く、こってりとした濃厚な味わいが特徴です。角煮や焼豚、ベーコンの原料としても使われます。カリカリに焼いて脂を落とす、サムギョプサルのような食べ方もおすすめです。 ・ロース肉 背中側の肉で、赤身と脂身のバランスが良く、きめ細かい肉質が特徴です。 豚肉本来の旨味を最も味わえる部位としても人気が高く、とんかつやポークソテー、生姜焼きなど、幅広い料理で主役を張れます。 (画像:肩ロース 脂質19.2g)
・低脂質な部位(疲労回復とダイエットのために) ・もも(モモ)肉 お尻まわりの、脂肪が少なく、きめ細かい赤身肉です。ビタミンB1も豊富に含まれています。 高温で加熱しすぎると硬くなりやすいため、薄切りにしてしゃぶしゃぶや炒め物、または、ブロックでじっくり煮込む(煮豚)料理に向いています。 ・ヒレ(ヒレ)肉 ロースの内側にある、細長い部位。豚一頭から、わずか1kgほどしか取れない、最もキメが細かく、柔らかい究極の赤身肉です。 そして、最も注目すべきは、このヒレ肉に、豚肉の中でも最も多くビタミンB1が含まれていることです。 脂肪はほぼゼロで、ビタミンB1は最強。 まさに「疲労回復の王様」と呼ぶにふさわしい部位です。 特に疲れがたまっている時は、このヒレ肉を使ったメニュー(ヒレカツやポークソテー)を選ぶのが、最も効果的です。
・ビタミンB1を無駄にしない、魔法の食べ合わせ ビタミンB1は、水に溶けやすく、熱に弱い、非常にデリケートな栄養素です。しかし、その吸収率を劇的に高めてくれる、魔法のようなパートナー食材があります。 それは、ニンニク、玉ねぎ、ニラなどに含まれる「アリシン」という匂い成分です。 アリシンは、ビタミンB1と結合すると、「アリチアミン」という物質に変化します。このアリチアミンは、ビタミンB1よりも熱に強く、体に吸収されやすく、さらに体内に長く留まって効果を発揮し続ける、というスーパービタミンなのです。 ・豚の生姜焼き(玉ねぎ使用) ・豚キムチ(ニンニク・ニラ使用) ・餃子(ニラ・ニンニク使用) ・豚ニラもやし炒め 私たちが愛する豚肉料理の多くが、驚くほど理にかなった組み合わせだったことが分かります。先人の知恵には、本当に驚かされますね。
豚はなぜ「鳴き声以外」食べられる? 知られざる豚肉雑学の世界
最後に、知っていると、豚肉との付き合いがもっと楽しくなる、豆知識をいくつかご紹介します。
・「鳴き声以外は全て食べられる」 これは、豚肉文化が発達した沖縄や中国で、古くから言われる言葉です。 ロースやバラといった正肉だけでなく、頭(カシラ)、舌(タン)、心臓(ハツ)、胃(ガツ)、腸(ホルモン)、子宮(コブクロ)、肝臓(レバー)、そして足(豚足)や、耳(ミミガー)、皮(チラガー)に至るまで、文字通り、捨てる場所がほとんどない、ということを意味しています。 これは、豚が、いかに効率的で、無駄のない家畜であるかを示すと同時に、食材の命を、最後の最後まで、ありがたく頂くという、食文化の知恵の表れでもあります。
・とんかつは、日本の発明品 とんかつは、西洋料理の「カツレツ(コートレット)」を、日本風にアレンジした、日本生まれの料理です。 薄切りの肉にパン粉をつけて、少量の油で「焼く」のがカツレツであったのに対し、分厚い肉に、たっぷりのパン粉をつけ、大量の油で「揚げる」という、独自の調理法へと進化させました。 キャベツの千切りを添える定番のスタイルも、日露戦争後、洋食店の人手不足を補うために、温野菜の付け合わせの代わりに、考案されたと言われています。
・沖縄の「スーチカー」 沖縄の伝統的な保存食で、豚のバラ肉を、塩漬けにして、熟成させたものです。 冷蔵技術がなかった時代に、豚肉を長持ちさせるための知恵ですが、塩漬けにすることで、余分な水分が抜け、旨味が凝縮され、生ハムのような、独特の風味を生み出します。
というわけで
今回は、「国民的食材」豚肉について、その驚異的な疲労回復効果と、健康的な側面を、徹底的に掘り下げてお話ししました。 豚肉は、ただ「脂が多い」のではなく、「疲れを吹き飛ばす、最高のビタミンB1供給源」であること。 そして、部位を賢く選び、アリシンなどのパートナー食材と組み合わせることで、そのパワーを、何倍にも高めることができること。 お分かりいただけたでしょうか。 疲れが溜まっているな、と感じた日こそ、ぜひ、ニンニクや玉ねぎをたっぷり効かせた、豚肉料理を食べて、体の中から、エネルギーがみなぎるのを、実感してみてください。
\ 一人で悩んでいませんか?お気軽にご相談ください! /
アンチエイジングアドバイザー Katsuの無料相談窓口
記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます!
「体に良いとは分っているけど、続けるのが難しい…」 「情報が多すぎて、何から始めたらいいか分からない」 「私のこの不調、どうしたらいいんだろう?」
もしあなたが今、そんな風に感じているなら、ぜひ一度お話を聞かせてください。 日々の食事や運動のこと、サプリメントの選び方、ちょっとした体の悩みまで、どんな些細なことでも構いません。
あなた専用の「かかりつけアドバイザー」として、親身にサポートさせていただきます。
【ご相談までの流れ】
- 下のボタンから、まずはLINEで「友だち追加」してください。
- 追加後、トーク画面からスタンプを一つでも送っていただけると、こちらからご挨拶のメッセージをお送りします。
- その後、あなたのペースでご相談内容をお聞かせください。
もちろん相談は無料です。安心して、下のボタンをタップしてくださいね。
▼公式LINEでKatsuに無料で相談してみる 無料で相談してみる
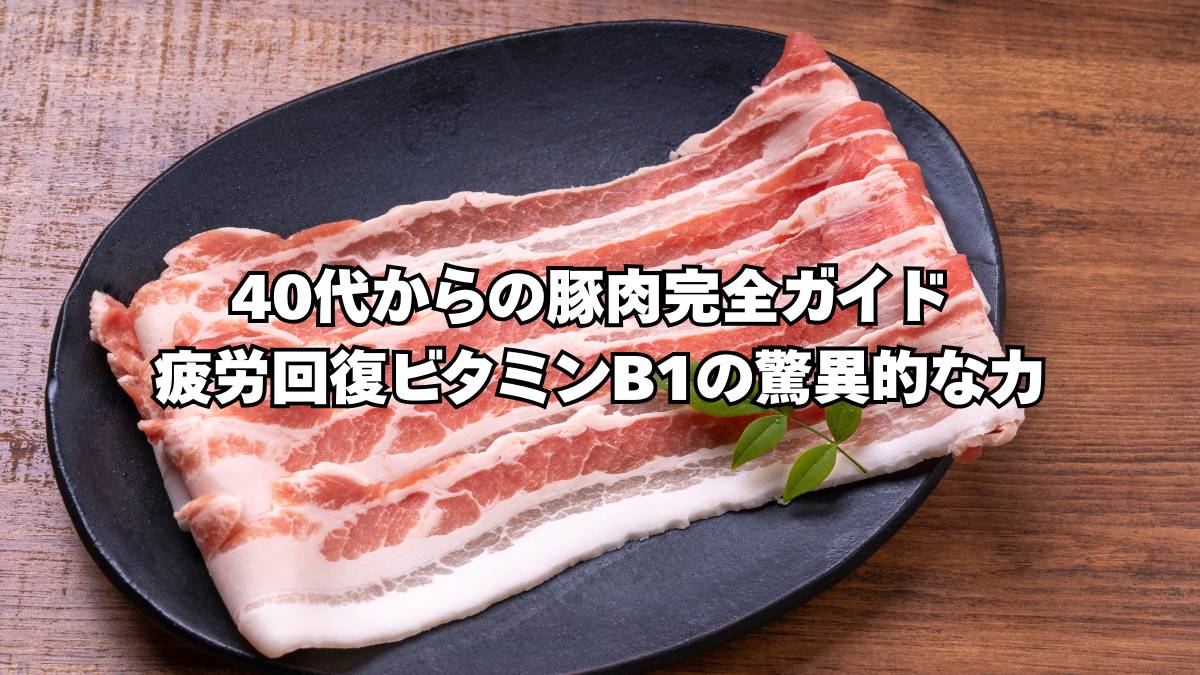
コメント