こんにちは!
アンチエイジングアドバイザーのKatsu(@adviserkatsu)です。
健康的な食生活を語る上で、決して欠かすことのできないスター選手、「魚介類」。 私たち日本人にとって、古くから食卓にのぼる、非常に馴染み深い食材ですよね。 「体に良い」ということは、誰もが知る常識ですが、その広大で奥深い世界を、私たちはどれだけ理解しているでしょうか?
マグロやサバといった赤身魚と、カレイやタイといった白身魚。その違いは、単なる色の問題なのでしょうか? そして、近年の健康ブームの中で、魔法の言葉のように語られる「EPA」や「DHA」。 これらが、具体的に私たちの体に、どのような素晴らしい効果をもたらしてくれるのか。
今回は、そんな魚介類の世界を深く探求し、単に「体に良いから食べる」という段階から一歩進んで、それぞれの魚が持つ「栄養的個性」を理解し、自分の健康目標に合わせて賢く選ぶための、新しい視点についてお話しします。
魚は、それぞれ専門を持つ「栄養のツールキット」である
まず、魚介類を、それぞれが異なる専門性を持つ「栄養のツールキット」だと考えてみましょう。 ある道具(魚)は体を作るのに優れ、ある道具は血液をサラサラにし、またある道具は脳の働きを助ける…。 それぞれの道具の特性を知ることで、私たちは、より効果的に、自分の体をメンテナンスすることができるのです。
道具の基本性能:すべての魚が持つ「良質なたんぱく質」
まず、すべての魚に共通する、最も基本的な性能。それが「良質なたんぱく質」の供給源である、ということです。 たんぱく質は、私たちの筋肉、皮膚、髪、そして免疫細胞まで、体を作るあらゆるものの主成分です。 特に魚のたんぱく質は、肉類に比べて脂肪が少なく、消化吸収が良いという特徴があり、40代以降の体にとっても、非常に効率の良い、優れた建材と言えます。
道具の種類を見分ける:赤身魚と白身魚の違い
次に、道具の種類を見分けてみましょう。魚は、見た目の色によって「赤身魚」と「白身魚」に分けられますが、これは単なる色の違いではありません。 その色の違いは、筋肉に含まれる「ミオグロビン」や「ヘモグロビン」といった、酸素を運搬・貯蔵する色素タンパク質の量によって決まります。
・赤身魚 マグロ、カツオ、サバ、アジ、イワシなど。 広大な海を、常に高速で泳ぎ続ける回遊魚です。長距離ランナーのように、大量の酸素を筋肉に供給し続ける必要があるため、ミオグロビンなどの含有量が多く、身が赤く見えます。
・白身魚 カレイ、ヒラメ、タイ、タラなど。 あまり長距離を泳ぎ回らず、海底や沿岸で静かに暮らしている魚です。瞬発力はありますが、持久力を必要としないため、筋肉中のミオグロビン量が少なく、身が白く見えます。
・サーモン(サケ)の秘密 ここで一つ面白いのが、サーモンです。見た目は鮮やかな赤色(オレンジ色)ですが、実は分類上は「白身魚」です。 あの色は、ミオグロビンによるものではなく、「アスタキサンチン」という、非常に強力な抗酸化作用を持つ、エビやカニと同じ色素成分によるものなのです。
最高の道具を選ぶ秘訣:「旬」を意識する
道具を選ぶ上で、非常に重要なのが「タイミング」です。魚でいうところの「旬」ですね。 魚の旬とは、一般的に、産卵を控えて、体に栄養をたっぷりと蓄えた、脂がのった時期のことを指します。 この時期の魚は、おいしさはもちろん、栄養も豊富です。 逆に、産卵を終えた後の魚は、人間のお産と同じように、体力を消耗し、痩せてしまっています。そのため、味も栄養価も落ちてしまいます。 最高の栄養価を求めるなら、その魚が最も脂を蓄える「旬」の時期を意識して選ぶことが、非常に賢い選択と言えるでしょう。
最重要ツール:「オメガ3脂肪酸」とは?
ここからが、今回の最も重要なテーマです。 近年の健康研究で、魚が持つ最も素晴らしい力として注目されているのが、その脂に含まれる「オメガ3系脂肪酸」です。 これは、私たちの体内で作ることができないため、食事から摂取する必要がある「必須脂肪酸」の一種です。 特に、青魚の脂に豊富に含まれる「EPA(エイコサペンタエン酸)」と「DHA(ドコサヘキサエン酸)」は、40代以降の私たちの健康を、多方面から力強くサポートしてくれます。
・EPAとは?「血液と血管の守護神」 EPAは、主に私たちの「循環器系」に対して、素晴らしい働きをします。 その役割は、まさに血液と血管の健康を守る「守護神」です。 主な効果として、 ・血液中の中性脂肪値を下げる ・血小板を固まりにくくし、血液をサラサラにする(血栓予防) ・血管の炎症を抑え、動脈硬化を防ぐ といった働きが知られています。高血圧や高コレステロール、動脈硬化といった、40代以降にリスクが高まる生活習慣病の予防・改善において、中心的な役割を果たす栄養素です。
・DHAとは?「脳と神経の最高の材料」 DHAは、主に私たちの「脳」と「神経系」にとって、不可欠な存在です。 その役割は、脳機能を支える「最高の建築材料」と言えるでしょう。 主な効果として、 ・脳や神経組織、目の網膜の主要な構成成分となる ・記憶力や学習能力といった、脳の認知機能を維持・向上させる ・精神を安定させ、抑うつ気分を和らげる といった働きが知られています。DHAは、脳が情報を伝え合うシナプスの膜を柔らかくし、情報伝達をスムーズにすると考えられています。「魚を食べると頭が良くなる」と言われる所以は、まさにこのDHAの働きにあるのです。
・EPA・DHAが豊富な魚 これらのオメガ3脂肪酸は、特に脂ののった青魚に豊富です。 サバ、イワシ、サンマ、アジ、マグロ(特にトロ)、ブリ、そしてサーモンなどが、優れた供給源となります。
・鮮度が命!酸化しやすいという弱点 しかし、この万能ツールには、一つだけ弱点があります。 それは、EPAやDHAが、非常に「酸化しやすい」ということです。 光や熱、空気に触れることで、その素晴らしい健康効果は失われ、逆に体に害を及ぼす「過酸化脂質」に変化してしまいます。 魚の健康効果を最大限に引き出すためには、何よりも「鮮度」が命。購入する際は、新鮮なものを選び、できるだけ早く食べ切ることが大切です。
魚介類のその他のツールと、安全マニュアル
魚介類のツールキットには、他にも様々な道具があります。 例えば、赤身魚の「血合い肉」の部分。見た目は少し敬遠されがちですが、実は、他の身の部分に比べて、貧血予防に役立つ「鉄分」や、カルシウム、そしてビタミンDが非常に豊富に含まれています。
一方で、道具を使う際には、安全マニュアルも必要です。 生のサバやアジ、イカなどには、「アニサキス」という寄生虫の幼虫がいる可能性があります。生で食べると、激しい腹痛を引き起こすことがあるため、加熱するか、一度冷凍することが、最も確実な対策となります。
というわけで
今回は、私たちにとって最も身近な健康食材「魚介類」について、それを「栄養のツールキット」と捉え、それぞれの道具(魚や栄養素)が持つ素晴らしい性能を詳しく見てきました。 赤身魚と白身魚の違い、栄養を最大限に摂るための「旬」の重要性、そして何よりも、脳と血管の健康を守る「オメガ3脂肪酸(EPA・DHA)」の計り知れないパワー。 お分かりいただけたでしょうか。
これからは、ただ漠然と「体に良いから魚を食べる」のではなく、「今日は脳のメンテナンスのためにDHAが豊富なサバを食べよう」「血管の大掃除のためにEPAを摂ろう」といったように、明確な目的意識を持って、魚を選んでみませんか? その賢い選択が、あなたの体を、内側から、より強く、より健やかに、作り変えていくはずです。
\ 一人で悩んでいませんか?お気軽にご相談ください! /
アンチエイジングアドバイザー Katsuの無料相談窓口
記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます!
「体に良いとは分かっているけど、続けるのが難しい…」 「情報が多すぎて、何から始めたらいいか分からない」 「私のこの不調、どうしたらいいんだろう?」
もしあなたが今、そんな風に感じているなら、ぜひ一度お話を聞かせてください。 日々の食事や運動のこと、サプリメントの選び方、ちょっとした体の悩みまで、どんな些細なことでも構いません。
あなた専用の「かかりつけアドバイザー」として、親身にサポートさせていただきます。
【ご相談までの流れ】
- 下のボタンから、まずはLINEで「友だち追加」してください。
- 追加後、トーク画面からスタンプを一つでも送っていただけると、こちらからご挨拶のメッセージをお送りします。
- その後、あなたのペースでご相談内容をお聞かせください。
もちろん相談は無料です。安心して、下のボタンをタップしてくださいね。
▼公式LINEでKatsuに無料で相談してみる 無料で相談してみる
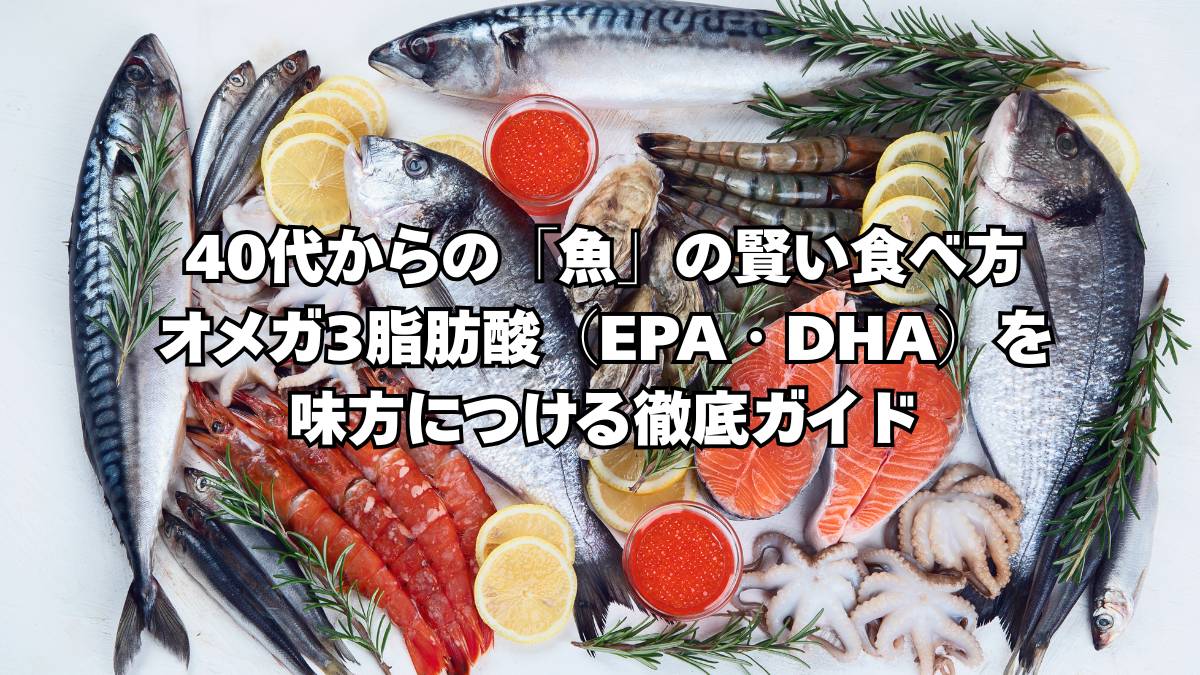
コメント